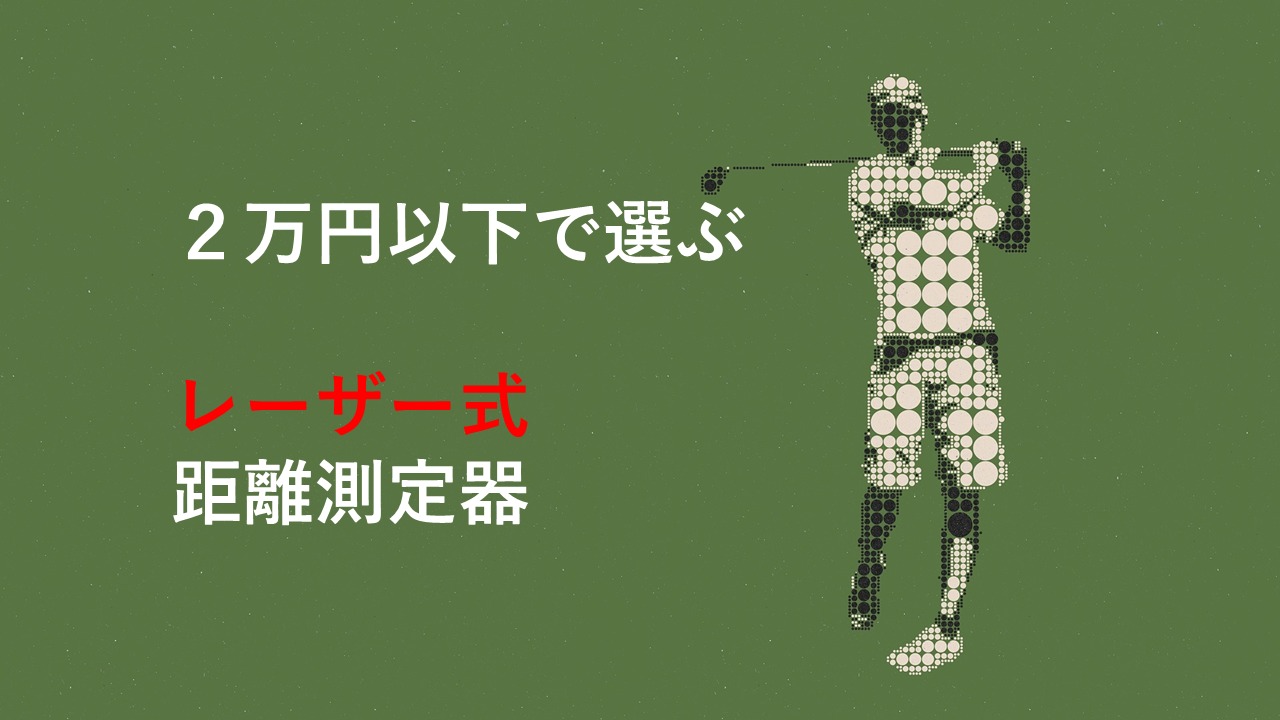ここ数年、距離測定器の売れ行きが上がっているようです。
その理由は、2019年のルール改正です。
それまでは、ローカルルールで使用が認められていましたが、ルール改正により原則使用可となり、ローカルルールで使用禁止することができるようになりました。
しかし、認められるといっても注意が必要です。
高低差(打ち上げ、打ち下ろし)などを加味する情報は、禁止されています。
距離測定器の中には高低差機能が含まれた製品もありますが、ほとんどがその機能のON/OFFをセットできるようになっています。
もちろん、競技ではないラウンド、つまり普段のプライベートラウンドで使う分には問題ありません。
GPS式とレーザー式はどっちがいい?

距離測定器にはGPS式とレーザー式があります。
GPS式は腕時計などのような身に着けるものが多く、手軽に計測できるのがウリです。
残り距離だけではなく、登録した地点からの距離も測ることができるので、例えば飛距離がどれくらいだったのかということも計測できます。
さらに、ログを保存できるので、あとで反省会をする時にも役立てることができます。
デメリットとしては、やはり誤差でしょう。
最近は、みちびき(準天頂衛星システム)に対応したモデルもあるので、この誤差は徐々に小さくなっているものの、やはりレーザーの正確さが勝ります。
レーザー式は、プレーヤーが任意の目標物までの距離を測る形式のものです。
単にピンまでの距離だけではなく、グリーンエッジ、池のふちなど、次のショットの目標や避けるべきハザードまでの距離を測ることができます。
一方、当然ながらブラインドとなっている対象は計測できませんので、その点はGPS式が有利と言えます。
多くのゴルフ場では、カートにナビが付いていますが、これはGPS式です。
実際のコースでは、このGPSを頼りにしながら、プレーヤーはレーザー式測定器を使用して打つべき距離を決めるというのがスマートな方法ではないでしょうか。
上手くないけど距離計は必要か?
測った距離など打てないから距離計など不要だ、という声も分からなくもありませんが、そういうゴルファーこそ距離計を使うべきです。
例えば、ピンまで残り100yだった場合で52度を選択したとしましょう。
もちろんダフったり、トップしてしまった場合は別ですが、それなりに普通に打てた時、果たしてどれくらいピンまでの距離が残ったのか、オーバーしたのかを確認するようにすれば、自分の本当の飛距離を知ることができます。
特に、グリーンを狙うショートゲームではキャリーの把握が必要です。
52度でうまく打ててもショートすることが多いのであれば、100yを打つのに52度では足りないということになりますね。
私はそれで、50度をバッグに入れるようになりました。
また、スコアを上げるにはハザードを徹底的に避けることも一つの戦略です。
ハザードまでの距離を把握して、フルショットしても届かないクラブで打てば、「もしかしたら入ってしまうかも」という心配もなくなります。
距離測定器は下手だから使わないのではなく、上手くなるために必要な道具なのです。
距離測定器の弊害

距離測定器が一般化する前まで、ホールサイドにある杭や立ち木などでおおよその残り距離を把握していました。
また、スプリンクラーなどにはグリーンセンター(ゴルフ場によってはエッジ)までの距離が1ヤード単位で書かれているので、そこから歩測で残り距離を測ったりしていました。
そのため、まず目視でおおよその距離を把握してクラブを持って行くので、見える景色で大体の距離が分かるようになりました。
例えば、セカンド地点にカートで移動している最中に、景色から大体の距離を把握して、クラブを数本持って行き、そこで距離計で測って、最終的なクラブを決めます。
しかし、毎回距離計で測ってしまうと、この距離感というのがだんだん失われてしまいます。
この距離感がないと、クラブを無駄にたくさん持って行くか、その場で測ってからカートに戻る必要があります。
また、30y程度のアプローチでも測るようになると、それこそスロープレーの原因になります。
距離を測る前に、景色から得られる情報で自分なりに距離を予想したうえで、測る癖をつけると距離感を失わず、むしろ養うことができると思います。
高低差計測機能は必要か?
例えば残り100yでも打ち上げの場合と打ち下ろしの場合では実際に打つべき距離が変わります。
高低差計測機能付きの測定器では、この差を加味して残り距離を表示してくれますので、番手選びの参考になるでしょう。
個人的には無くても何とかなるというのが感想です。
でも、最近では高低差機能が付いていてもリーズナブルなモデルが出ているので、ないよりあったほうが後々助かるということになるかもしれません。
なお、既述の通り、競技では使えませんのでご注意ください。
2万円以下で選ぶ初めての距離測定器
初めて距離測定器を購入するのに、あまり高いものは必要ありません。
最初はリーズナブルなものを使って、上達してから上位モデルを買うことをお勧めします。
Nikon COOLSHOT 20i G II
安心のNikon製
130gの軽量ボディーで、ポケットに入れても邪魔になりません。
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載しており、奥の目標物までの距離を測定してしまうことが避けられます。
アイリスオーヤマ YARD SCOPE YS20
非常に安いので、とりあえず距離計を手に入れたい人向き。
安くても機能はしっかりしていて、この価格で高低差も測ることができます。
重量も120gと軽量で持ち運びにも便利です。
GOLFZON CaddyTalk minimi
重量はほかの製品と大して変わりませんが、サイズが小さいので持ち運びやすいモデルでしょう。
こちらも高低差計測機能付きですが、バッテリーが充電式です。
電池式は電池交換すればいいので出先でも何とかなりますが、充電式はそうもいきません。
とは言え、1ラウンドで切れてしまうことはないでしょうが、こまめに充電できる人向けですね。
ちなみに、GOLFZONというのは韓国系の会社のようで、ウェブサイトの日本語が若干変なのはご愛敬ということで。
TecTecTec TecTecTec Mini
特徴的な名前のメーカーですが、フランスに本社があるメーカーのようです。
このメーカーのウェブサイトも面白いのでぜひ見てみてください。
非常に小さく軽いので、ポケットに入れても邪魔になりません。
それでいて、高低差計測機能のほか、振動(バイブレーション)機能も付いていたりと、結構ちゃんとしています。
電源が、電池式なのか充電式なのか、どこを見ても不明でした。
お勧めレーザー式距離測定器製品別まとめ
| 製品名 | メーカー | 重量 | 高低差 | 電源 |
| COOLSHOT 20i G II | Nikon | 130g | ○ | CR2リチウム電池 |
| YARD SCOPE YS20 | アイリスオーヤマ | 120g | × | CR2リチウム電池 |
| CaddyTalk minimi | GOLFZON Japan | 135g | ○ | 充電式 |
| TecTecTec Mini | TecTecTec | 118g | ○ | 不明 |
最初に購入するモデルとしては、やはりNikonが安心できます。
これなら、壊れない限り買い替える必要がないと思います。
.png)